|
||||||||||||||||||||
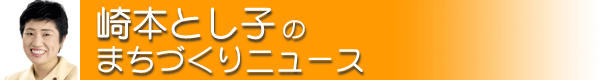 |
||||||||||||||||||||
第2回おかやま環境フォーラム
|
| 3月27日、第2回おかやま環境フォーラムが開催された。分科会6つはどれも興味深い。崎本市議は第3分科会に参加。午後のパネルディスカッションにも耳を傾けた。
「いのち」と「環境」はきりはなせない。地球のいのちにもしっかり関心をもとう。 |
分科会第一分科会 「海の森」アマモ場の再生に向けた岡山県での取り組み/環境問題と防災問題の整合の必要性「台風23号で倒木被害、山林の再生を、2次災害を防ごう」 第二分科会 岡山海域の海岸生物調査経過報告/岡山の淡水魚の状況/カブトガニと笠岡の海況異変 第三分科会 大気汚染の原因と健康への影響/地域環境と交通問題 第四分科会 くらしの工夫や意識の変化/くらしと環境 第五分科会 環境塾について/企業の環境対応を広げる 第六分科会 渋川海岸清掃ロボットコンテスト/環境教育への報告資料 それぞれの分科会では「プレ分科会」の概要報告なども行われました。 |
「第2回おかやま環境フォーラム宣言」
|
「崎本とし子のまちづくりニュース」Web版
発行:日本共産党岡山市議団 岡山市大供1-1-1 市役所内
電話:086-803−1000 (内線4370)/ Fax:086-234-9388(直通)
[TOP]